看護職キャリア支援センター教育プログラム開発部門では、令和7年度第1回医療的ケア児支援講演会を、テーマ「ここからはじまる・ひろがる~医療的ケア児の学校生活を考える~1型糖尿病当事者が伝えたいこと~」のもと、ハイブリッド形式で開催しました。今回の講演会は参加制限を設けず、どなたでも参加できる形式とした結果、会場参加45名、Zoom参加134名、合計179名と、多くの方々にご参加いただきました。参加者は北海道内にとどまらず、道外や海外からもあり、さらに医療的ケア児当事者やご家族の参加もみられました。
講演では、医師・当事者・家族といった多様な立場から、4名の講師にご登壇いただきました。
最初に、旭川医科大学小児科医員の山村日向子先生より「1型糖尿病ってなに?~小児科の診察室から~」と題してご講演いただきました。1型糖尿病に関する基本的な知識に加え、就学に向けた準備の重要性について解説され、特に「学校と病院の連携による支援体制の必要性」と「将来、患者が自立して生活できるよう自己管理を支援することが最大の目標である」というメッセージが強く印象に残りました。
続いて、1型糖尿病当事者である梶屋諒人様より「僕が走る理由〜自転車と挫折と音楽という夢〜」をテーマにご講演いただきました。糖尿病と向き合いながら学校生活を送る困難さ、それを乗り越え夢を追い挑戦し続ける姿、そしてその過程における葛藤が語られ、参加者に深い感動を与えました。さらに、教育者であり諒人様の父親でもある梶屋明広様からは、当事者を支える家族のあり方や、学校関係者との協働の重要性について示唆に富むお話をいただきました。
次に、1型糖尿病当事者である田村鈴花様からは「うまくやりな~合理的配慮の使い方」と題してご講演をいただきました。1型糖尿病を発症してからの学校生活において、教員・養護教諭・クラスメートとの関わり、そして学校における合理的配慮のあり方について、具体的な経験をもとにお話しいただきました。特に、通学する学校が変わることで、それまでスムーズに行えていたことが困難となり、結果として学校に通うこと自体が難しくなってしまう場合があることが示され、当事者・教員・主治医・家族が連携することの重要性を改めて考えさせられる内容でした。最後に田村様から「Ⅰ型糖尿病の理解者になってください」と参加者に向けて投げかけられた言葉は非常に印象的であり、当事者にとって周囲の理解がいかに大切であるかを強く実感させるものでした。
今回の講演会を通じて、医療的ケア児をめぐる支援の在り方について、多角的な視点から学びを深めることができました。今後は、学校と医療機関、家庭、地域がより一層連携し、当事者が安心して学校生活を送れる環境づくりを推進していくことが求められます。看護職キャリア支援センター教育プログラム開発部門では、今後もこうした学びの場を継続的に提供し、医療的ケア児とその家族がより安心して学校生活を送れる社会の実現に貢献してまいります。

【受付】
看護職キャリア支援センター
教育プログラム開発部門
塩谷今日子 部門員・看護師長
本村勅子 部門員・看護師長
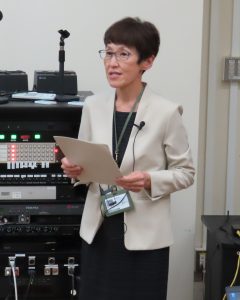
【司会】
看護職キャリア支援センター
教育プログラム開発部門
原口眞紀子 部門長・准教授

【開会挨拶】
看護職キャリア支援センター
升田由美子 センター長・教授

【講演「1型糖尿病ってなに?~小児科の診察室から~」】
旭川医科大学病院小児科医員
山村日向子 先生

【講演「僕が走る理由〜自転車と挫折と音楽という夢〜」】
梶屋諒人 様

【講演「僕が走る理由〜自転車と挫折と音楽という夢〜」】
梶屋明広 様

【講演「うまくやりな~合理的配慮の使い方」】
田村鈴花 様

講演会の様子





