トップページ 耳鼻咽喉科豆知識 / 頭頸部癌 頭頸部癌の種類
頭頸部癌の種類
1. 鼻・副鼻腔癌
鼻腔(鼻の中)の周囲には、図のように副鼻腔という大きな空洞がいくつも存在します。この部位から発生する癌を、鼻腔または副鼻腔癌といいます。
【図1】
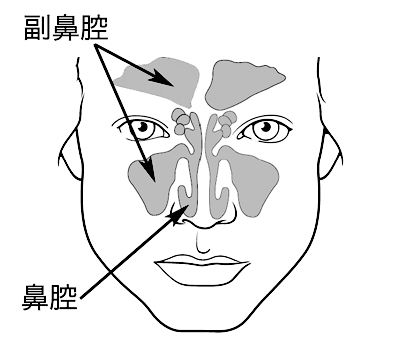
症状
鼻血が続く、
検査
片方の鼻閉(鼻づまり)が良くならない、
目や頬部(ほお)が腫れている、
頬部がしびれる、頬部や鼻が痛い、
など視診 まず鼻腔内を直接目で見て診察します。さらに内視鏡(ファイバー)を用いて詳しく観察します。
治療
触診 頸部に転移したリンパ節がないか触診します。
単純X線(レントゲン)検査 副鼻腔は骨で囲まれた空間で、病変を十分に診察できないために画像診断が必須です。単純X線検査は最初に行われる一般的な検査です。
超音波(エコー)検査 頸部への癌の転移がないかを調べます。
CT検査、MRI検査 X線検査では十分にわからないような深部での癌の広がりなど様々な情報が正確に得られます。また癌の頸部への転移や、肺や肝臓など他臓器への転移の有無も調べられます。
核医学検査(シンチグラム) 癌の他の臓器への転移がないか(遠隔転移)を調べます。
生検 癌の一部を直接採取し、癌の組織型(性質)を調べます。浅側頭動脈(耳の前方にある動脈)からカテーテルを入れて抗癌剤を注入します。さらに放射線療法も同時に行います。これらの治療によって癌を縮小させてから、手術にて癌を摘出します。摘出範囲が大きく顔面の変形が予想される場合には、遊離皮弁による再建術を行います。また手術不能な進行癌では、超選択的化学動注療法を行うこともあります。
2. 舌癌、口腔癌
舌や口腔(口の中)の粘膜からできる癌です。アルコールや喫煙、口腔内の不衛生な状態などの慢性的な刺激が原因といわれています。
【図2】

症状
舌や口の中の痛みが良くならない、
検査
大きな口内炎ができて治らない、
口の中がはれている(できものがある)、
食事の時に痛みや違和感がある、
首がはれてきた、
など視診:口腔内を直接目で見て、癌の大きさや形などを診察します。
治療
触診:触診により、癌の硬さや周囲への広がりなどを調べます。また頸部に転移したリンパ節がないか触診します。
内視鏡検査、単純X線検査:必要に応じて、適宜追加します。
超音波(エコー)検査:頸部への転移がないかを調べます。
CT検査、MRI検査:深部への癌の広がり、頸部や他臓器への転移の有無を調べます。
核医学検査(シンチグラム):他の臓器への転移(遠隔転移)がないかを調べます。
生検 癌の一部を直接採取し、癌の組織型(性質)を調べます。早期癌であればレーザー切除術を行います。手術の結果や、癌の進行度によっては放射線療法や化学療法の併用が必要となります。また手術不能な進行癌では超選択的化学動注療法を行うこともあります。
3. 上咽頭癌
上咽頭は図3のように鼻腔の奥にあり、咽頭(のど)の一番上の部分です。ここにできる癌を上咽頭癌といいます。上咽頭癌の発症には、EBウィルスというウィルスが関与しているといわれています。また耳管という耳に通じる管の出口に近いため、中耳炎を起こすことがあります。
【図3】
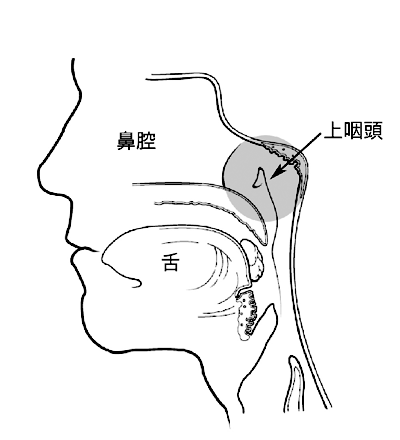
症状
鼻がつまって良くならない、
検査
首がはれてきた、
鼻血が続く、
食事の時に痛みや違和感がある、
耳が遠くなった(中耳炎を繰り返すようになった)、
など視診:上咽頭は直接見ることができないため、後鼻鏡という小さな鏡を使って診察するか、内視鏡検査による診察が必要になります。
治療
触診、超音波(エコー)検査:頸部に転移したリンパ節がないかを調べます。
CT検査、MRI検査:上咽頭は体の深部に位置し、周囲に重要な臓器も多いため必須の検査です。またCTは遠隔転移の検査にも用いられます。
核医学検査(シンチグラム):他の臓器への転移(遠隔転移)がないかを調べます。
生検:主に内視鏡下に癌の一部を直接採取し、癌の組織型(性質)を調べます。放射線と抗癌剤による化学療法が主体となります。手術治療は一般的ではありませんが、頸部に転移したリンパ節が残存した場合に頸部郭清術(頸部リンパ節とその周囲組織を一塊に摘出する手術)を行うことがあります。また超選択的化学動注療法を行うこともあります。