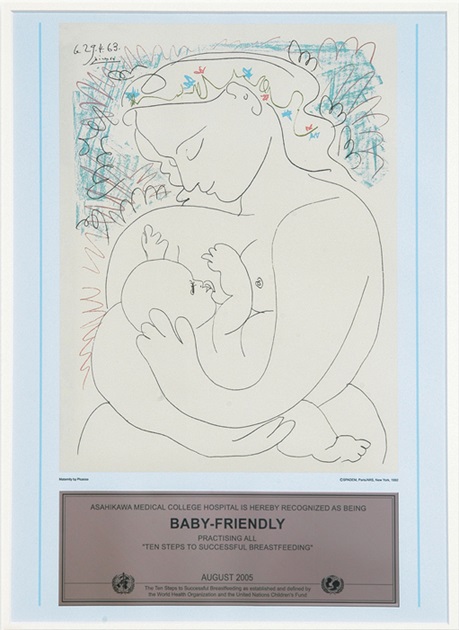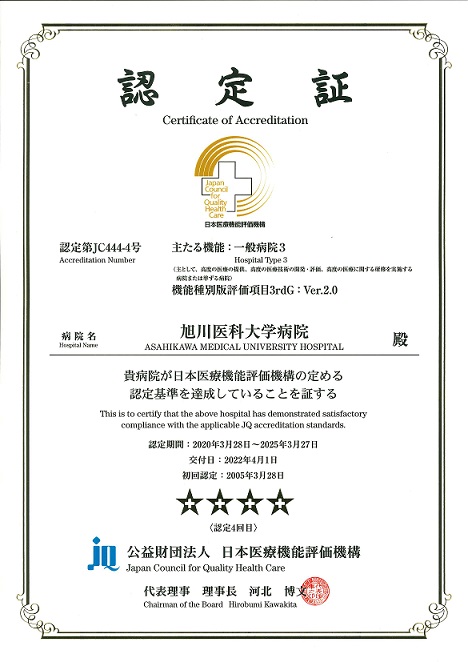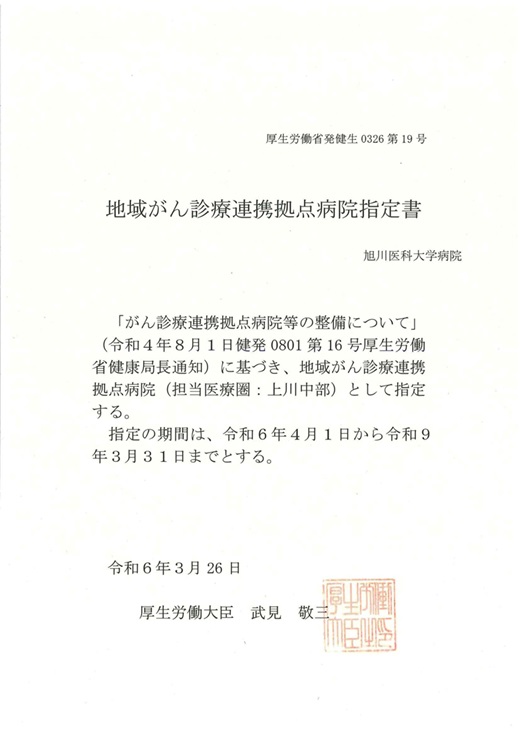眼科
診療科について
眼科学講座は昭和50(1975)年に開講、初代保坂明郎教授によって講座の基礎が築かれ、令和5年から4代目長岡泰司教授が就任しました。当教室は網膜循環(網膜の血液の流れ)の診療、研究に精力的に取り組んできたことから、伝統的に網膜硝子体疾患の診療が充実しています。
開講から約50年が経とうとしていますが、目を取り巻く環境も様変わりしてきました。社会の高齢化、デジタルデバイスの登場により目の病気も多様化してきています。画像診断技術の飛躍的な進化に伴い新たな疾患概念も誕生しています。眼科学講座では多くの専門外来を有し、これらの時代に伴う変化にも柔軟に対応し、最新の治療を提供しています。
専門外来に関しては、以下に詳細を記述していますのでご参照ください。ほぼ全ての分野を網羅しています。しかしより専門的な診断、治療が必要と判断した場合には、全国の大学病院、研究施設と連携して、最適な診断、治療を患者様に提供できるよう心がけています。
このような体制のもと研修医の教育にも力を入れていて、幅広い臨床経験と各分野での高度で専門的な知識と技術の習得を目指し、優れた力量を有する総合力のある眼科医育成を目標としています。その後関連施設に勤務することにより、道内各地の眼科医療に貢献しています。また最近では、各関連施設との連携をより密にしていて、勉強会などの情報交換会を頻回に行っています。各施設における診断、治療の情報を共有し、最新の情報をアップデートすることにより、大学のみならず関連施設においても高い診療レベルを維持しています。
スタッフ紹介
教授
長岡 泰司ナガオカ タイジ
教授(眼科地域医療創生講座)
木ノ内 玲子キノウチ レイコ
准教授
横田 陽匡ヨコタ ハルマサ
講師
西川 典子ニシカワ ノリコ
講師
善岡 尊文ヨシオカ タカフミ
学内講師
神谷 隆行カミヤ タカユキ
学内講師
宇都宮 嗣了ウツノミヤ ツギアキ
助教
今野 杏美コンノ アミ
助教
大坪 充オオツボ ミツル
診療助教
阿部 翼アベ ツバサ
外来診療担当医表
当診療科の「外来診療担当医表 」は下記リンクよりご確認ください。
主な診察内容の紹介
旭川医大眼科には、様々な病気に対し正確な診断と適切な治療を提供できるよう、糖尿病網膜症、黄斑疾患、緑内障、角膜、ぶどう膜・眼炎症・斜視弱視、ロービジョン外来等の専門外来を開設しています。
診察は完全予約制です。受診される場合は原則、他の医療機関からの紹介状(診療情報提供書)と診療日時の予約が必要です。また、当院での専門的な診断や治療を終えられた患者様には、地元の病院や近隣のクリニックで「かかりつけ医」の先生に診ていただくという「地域医療連携」を推進しております。
糖尿病網膜症
糖尿病網膜症とは、血糖値が高い状態が長く続くことにより、目の網膜に広がっている毛細血管が傷害され、失明に至ることもある病気です。重症になるまで視力低下などの自覚症状がないため、糖尿病と診断されたら眼科の受診が必要となります。全世界の糖尿病患者さんのうち、何らかの糖尿病網膜症をもつ患者さんは約3人に1人とされており、糖尿病網膜症をもたない患者さんでも年間に4%は糖尿病網膜症を発症すると言われています。糖尿病による失明予防のためには血糖コントロールが基本ですが、定期的な眼底検査が必要不可欠です。
糖尿病網膜症の診察や治療をする上で、大変有用な多くの診療機器を取り揃えています。
蛍光眼底造影検査:腕から造影剤を注射して、眼の血流状態を確認します。
光干渉断層計(OCT):短時間で網膜の断層像を詳細に得ることができます。
光干渉断層血管撮影(OCTA):造影剤を使用することなく、眼の血流状態を確認します。何枚か画像を組み合わせて、広画角の撮影が可能な機種も使用しています。
レーザースペックルフローグラフィー(LSFG):レーザーの反射光を測定し、血流の分布を可視化できる装置です。
治療は、従来から行われている、進行した糖尿病網膜症に対する網膜光凝固術(レーザー治療)や硝子体手術も行っています。パターンレーザーといって、治療時間が短く、痛みの少ないレーザー機器での治療が可能です。視力に最も大事な部分である黄斑がむくんでしまう、糖尿病黄斑浮腫に対しては、ステロイドや抗VEGF抗体などの薬物を注射する治療も、外来で当日に行うことが可能です。症例に合わせて、最良の治療法を提案させていただきますので、ご不明な点がございましたらご遠慮なくお申し付けください。
黄斑疾患
黄斑とは、網膜の中心に位置し、眼の中に入った光が焦点を結ぶ場所を黄斑といい、文字や色を識別するために重要な細胞が集まっている場所です。良好な視機能を保つ上で最も大切な場所と言えます。
黄斑部の病名として、
- 加齢黄斑変性
- 強度近視、網膜色素線条症や中心性滲出性網脈絡症に伴う血管新生黄斑症
- 黄斑円孔
- 黄斑前膜
- 中心性漿液性脈絡網膜症
などの黄斑部に異常をきたす疾患があります。
黄斑疾患の症状として、
- 物がかすんで見える
- 物がゆがんで見える
- 視力が低下した
- 中心部が見づらい
- 物が小さく見える又は大きく見える
このような症状を自覚した場合は眼科で検査を受けることをお薦めします。
当院検査には、
黄斑部疾患に対し診察、治療する上で大変有用となる多くの最新眼科機器を取り揃えています。
視力検査や眼底検査などの一般検査を行った後、必要に応じて以下の検査を行います。
蛍光眼底造影検査(HRA):2種類の造影剤(フルオレセイン及びインドシアニングリーン)の同時撮影が可能
光干渉断層計(OCT):網膜の断層像を詳細に得ることが可能。現在4種類のOCTが稼働中。
光干渉断層血管撮影(OCT-A):網膜・脈絡膜の血管を詳細に得ることが加納。現在3種類のOCT-Aが稼働中。
マイクロペリメータ(MP-3):眼底を観察しながら視野検査が可能
多局所網膜電図:網膜の局所的な電気生理機能の評価が可能
治療として、
それぞれの検査結果から総合的に診断をした後、硝子体手術、レーザー治療、薬物療法による適切な治療を行います。特に、近年増加傾向にある加齢黄斑変性に対しては、以前から行われているレーザー治療に加えて、光線力学的療法(PDT)、薬物(抗VEGF抗体)の硝子体内注入を行っております。血管新生黄斑変性に対して十分なインフォームドコンセントを行った後、抗VEGF抗体の硝子体内注入を行っています。抗VEGF抗体の進歩が目覚ましく各疾患に応じた薬物、治療プロトコル選択を行なっています。
角膜・涙道
「目の表面とドライアイについて」
角膜は目の表面のいわゆる「くろめ」のことをいいます。角膜は、目の中に光を通すためにいつも透明で正しい形を保っている、とても精巧に出来たレンズです。
角膜を透明に保つためには涙液がかかせません。涙液はつねに目の表面をうすくおおい、角膜にきずが付いたり、ごみや雑菌が入ったりしないようにしています。涙液のようすが壊れると、角膜の透明性や形がくずれ、正しくものがみえなくなります。
「ドライアイ」という状態が広く知られるようになりました。涙液が不足したり、性質が整わなくなったりすると、角膜がうまく働きません。涙液のようすを健康に保つことはとても大切なことです。
角膜涙道外来では、皆さんの目の表面が健康であるかについて診察をしています。目が乾く、ゴロゴロする、痛みがある、涙がでなかったり、出過ぎたりするといった症状はドライアイかもしれません。
ドライアイのみなさんには人工涙液や角膜保護剤といった点眼薬を処方します。症状に合わせてその分量や種類を調節して用います。また、涙点プラグや涙道留置チューブといった、涙のたまっている量を調節する処置をすることもあります。ドライアイの症状は生活習慣でも大きく変わりますので、生活指導も組み合わせています。
「角膜移植について」
眼科医は患者さんの目を守るべく日頃の診察を心がけていますが、病気の種類や程度によっては 重い後遺症が残ってしまうこともあります。角膜が病気やけがで濁ってしまい、視力が低下してしまった場合、角膜の透明性を取り戻す方法に角膜移植があります。
眼に病気をしたことのない方が亡くなったとき、角膜を提供するご意志が有る場合、献眼が行われます。献眼とは、その方の死後、病気の人のために角膜を提供することです。こうして提供された角膜は、精密検査によって手術にふさわしいかを調べた上で、角膜移植を待っている患者さんに公平に分配されます。ひとりの提供者から2つの角膜が得られますので、2人の患者さんの光を取り戻すことが出来ます。
角膜涙道外来では、角膜の病気で移植を待っている患者さんの診察と手術を行っています。また旭川医大アイバンクを組織し、角膜提供者の登録、献眼の増加のための啓発活動を行っています。
未熟児網膜症
未熟児網膜症外来では、月曜と金曜の午前中に、旭川医大の新生児集中治療室(NICU)の病棟に出張し、未熟児網膜症の疑いのある新生児に対して細隙灯検査、眼底検査を実施しております。さらに慎重な経過観察が必要な症例には、週2~3回の診察を行っています。未熟児網膜症は、在胎週数34週未満、出生体重が1800g未満の低出生体重児が生後3~6週ごろに発症しやすい、網膜の血管の未熟性に基づく疾患です。網膜血管は胎生9ヶ月頃にほぼ完成するとされていますが、それ以前に出生した場合、眼球内での酸素濃度を含めた環境の変化により、網膜血管の異常成長を引き起こし発症します。悪化すると網膜剥離に進行し、失明の危険にさらされます。
近年、未熟児管理が進歩して低出生体重児の生存率が高くなるにつれ、重症の未熟児網膜症症例は増加しています。進行例に対しては、新生児の負担を最小限に抑えつつ、抗血管内皮増殖因子(anti-VEGF)の硝子体注射や双眼倒像を用いたレーザー治療を実施します。さらに、網膜剥離まで進行した症例には、冷凍凝固、バックリング術、硝子体手術などで対応します。
治療時期の見極めが大変重要ですが、自然治癒の可能性を十分考慮しながら、治療効果の適正時期を逃さぬよう細心の注意を払って診療を行っています。
午後からは、抗血管内皮増殖因子硝子体注射やレーザー治療を受けたNICU退院後の未熟児網膜症患児を中心に眼底検査を予約にて適宜行っています。
緑内障
旭川医科大学眼科では毎週火曜日午前、木曜日午前に緑内障外来を開設しており、他の医療機関からご紹介いただいた患者様の診療にあたっております。
緑内障は日本での失明原因として最も多い病気です。40歳以上の人のおよそ20人に1人が緑内障と言われていますが、病気が進行するまでは症状がなかなか出ないことも多いです。緑内障でダメージを受けた神経を元に戻すことは残念ながら現在の医学ではできませんが、目の圧を下げることで進行を緩やかにできるとされています。
当院緑内障外来では最新の画像診断装置を併用することにより、より精度の高い緑内障診療を提供しております。最も割合の多い開放隅角緑内障では、点眼による薬物治療、レーザー治療を行い、それでも不十分と判断される場合は手術を検討します。当院では線維柱帯切除術、線維柱帯切開術(眼内法、眼外法)、チューブシャント手術、プリザーフロマイクロシャント手術、白内障手術併用眼内ドレーン挿入術などを年間約200例実施しており、経験豊富な医師による施術と術後管理を受けることが可能です。緑内障には多くの病型があり、治療法も病型によって異なります。我々は、個々の患者様の緑内障病型、年齢、重症度、眼圧の経過などに応じて、患者様に応じた治療を提案しています。
ぶどう膜・眼炎症
ぶどう膜炎とその他の眼炎症性疾患の診療を行っています。
ぶどう膜炎とは、眼の中の血管の豊富な膜である脈絡膜・毛様体・虹彩を中心に炎症を起こす病気です。原因としてはウイルス感染や自己免疫などいろいろあり、弱い炎症ですぐに治るものから、強い炎症で長引いたり繰り返したりするものまであります。
当院では他の眼科クリニックから紹介いただき、原因検索や治療が必要な方の診療を行っております。診療の流れとしては、まず原因の特定をできる限り進めます。また、同時に炎症の状態にそった治療を行います。その後、原因が明らかになったところで、それに即した治療を加えていきます。ベーチェット病や重症難治性ぶどう膜炎に対しては、抗TNF-α抗体も使っており、視機能の維持改善に効果をあげています。
ぶどう膜炎の他に、強膜炎や血管炎(側頭動脈炎・ANCA関連血管炎・SLEなど)により眼に障害を起こした際の治療も内科と連携し行っています。
それぞれの疾患、それぞれの患者様に、最善の治療のできるよう心がけて、診療しております。
斜視・弱視外来
斜視・弱視の専門外来では、視能訓練士と連携して検査や治療を行っています。
斜視とは、両眼の視線が同じ方向を向いていない状態で、どちらかの目が内に寄る内斜視、外を向く外斜視、上や下にずれる上下斜視があります。斜視は乳児から成人まで幅広い年齢に発症します。
斜視の治療法は主に手術ですが、それぞれの病状に応じて、適切な眼鏡、視能訓練、プリズム眼鏡、ボツリヌス毒素注射等を組み合わせて治療を行っています。
弱視は、強い屈折異常(遠視、近視、乱視)や斜視などが原因で小児期に正常な視力の発達が妨げられた状態です。近年、3歳児健診に屈折検査が導入され、弱視のお子さんが早期に発見される ようになってきました。弱視治療は小学校入学前までが特に重要です。眼鏡装用、健眼遮閉訓練(アイパッチ)、点眼薬による治療を行います。視力の発達しやすい時期を逃さないよう、早期に適切な治療を行うことを目指しています。
ロービジョン
視覚障害を有する患者さんに対し、残された視機能を有効に使うために適切な補助具を選定しケアを行う専門外来です。視覚障害の程度に関わらず視覚に障害があるため生活に何らかの支障を来している方すべてを対象としています。全く見えない場合でも、映像を音声に変換して情報を提供してくれる補助具(エイド)があります。
ルーペや拡大読書器など拡大によって物を見やすくするロービジョンエイドの選定や使い方の指導、見え方が悪くなることを出来るだけ抑えながらまぶしさを取り除く遮光眼鏡の処方、日常 生活用具や便利グッズの紹介などを行っています。さらに、スマートフォンをはじめとする携帯 端末のアプリの紹介と指導、白杖の選定に関する相談から白杖を使う歩行訓練、自分で化粧が出来るブラインドメイクの指導なども行っています。
ケアのために十分な時間を確保するため、通院中の眼科主治医からの完全予約制となっています。
外来のご案内
眼科:1階11番

入院のご案内
眼科:8階東病棟