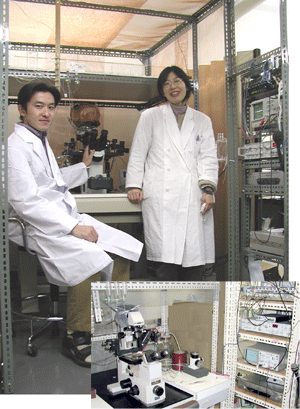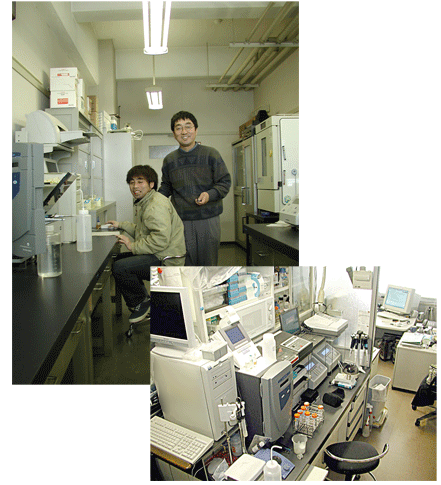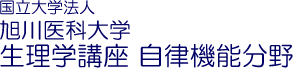
| 研究室紹介 | ||||||
|
||||||
当講座は、1973年(昭和48年)の本学開学当初から2001年3月まで教授を務めた黒島晨汎現名誉教授のもとに発足しました。2001年10月に後任の高井が名古屋大学より第二代教授として着任し現在に至っています。 メンバーは、2010年4月現在、教授1,講師1,助教2,事務補助員1の5名に加え、院生2名(眼科からの派遣1名を含む)、共同研究者2名(中国からの外国人客員研究員1名を含む)合計9名です。 |
||||||
細胞生理学グループ (高井) 視覚遠近調節でおなじみの毛様体筋の収縮調節メカニズムに関する研究を電気生理学と分子生物学の両面から進めています。現在、副交感神経刺激に伴って開口し収縮持続相に必要な細胞外からのカルシウムイオン流入経路を形成する新規陽イオンチャネルのクローニングと機能解析に取り組んでいます。 また、プロテインフォスファターゼとその特異的阻害剤の研究を内外の研究者と共同で行っており、最近は特に、新規微量フォスファターゼ群の同定・クローニングと、それらのイオンチャネル開閉調節など生理機能における役割に関する研究に力を入れています。 |
||||||
|
||||||
温熱生理学グループ (橋本) 冬眠動物における脳の代謝物質、脳血流に関する研究をおこなっています。現在、代謝関連物質の遺伝子発現の変化について、冬眠から覚醒に至るまでの経時変化を追う実験を進めているところです。 また、人工炭酸泉浴の生理機能への作用に関する基礎実験でも成果を挙げています。 |
||||||
|
||||||
本学学生のみなさんへ 生理学は,誰にもなじみ深い健康な体の働きのメカニズムを研究対象とする、もともと非常に取っつきやすくて面白い学問です。(参考、日本生理学会HP) それは、一見ずいぶん込入った実験装置を必要とするようになった現在でも実は全く変りません。 どうか一度、私たちの研究室を気軽に覗いてみて下さい。 |
||||||
since |
||||||
| 〒078-8510 旭川市緑が丘東2条1の1の1 | ||
| 旭川医科大学 生理学講座 自律機能分野 | ||
| 電話: 0166-68-2322 / FAX: 0166-68-2329 |