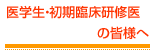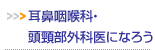第18回日本口腔・咽頭科学会
会長 原渕保明(旭川医大)
第18回日本口腔・咽頭科学会は旭川医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室の担当で、平成17年9月9日(金)、10日(土)の2日間にわたって、旭川市の旭川グランドホテルで開催された。当教室では初めての全国学会であったが、学会役員や会員の先生方のご協力で盛会に終えることができた。紙面をお借りして心から感謝申し上げたい。地震と台風がないというのが旭川のひとつの売りであったが、週の前半に台風14号が北海道を直撃するという予報もあり、一時は天候を危ぶまれた。しかし、幸いにも台風14号は8日未明に旭川を通り過ぎ、8日夕方の役員会をはじめ、会期中は秋晴れで、一足早い旭川の秋を堪能された参加者も多かったと聞いている。



日本口腔・咽頭科学会は18回と比較的歴史の浅い学会と思われている方も少なくないと思われるが、平成4年、第5回開催時に扁桃研究会と合併し、今日に至っている。したがって、前身の扁桃研究会の歴史32回を加えると今回は45回目となる。さて、本学会を企画するにあたり、キーワードを2つ設けた。ひとつは、「ザ口腔・咽頭」ということで、扁桃、睡眠時無呼吸症候群、腫瘍、唾液腺、味覚といった口腔・咽頭領域全般にわたって特別企画を組んだ。もうひとつは「ザ旭川」ということで、特別講演と市民公開講座には旭川の動物園園長と旭川医大の先生に講演を依頼した。そして、シンポジウム、セミナー、特別講演を主に1日目午後、2日目午前に組み、特別企画に数多くの参加できるようにした。



一般演題は今までで最も多い167題の応募があり、参加者も450名を超えた。一般演題の内容は扁桃31題、腫瘍27題、睡眠時無呼吸症候群22題を始め、唾液腺、味覚、嚥下、感染症、逆流症など口腔・咽頭科学全般に漏れ巻く集まり6会場を使って活発な発表、討論がなされた。



シンポジウムは、口腔・咽頭科学のトピックスである睡眠時無呼吸症候群、扁桃病巣疾患、口腔・咽頭癌の3テーマを企画した。シンポジウム1「睡眠時無呼吸症候群の診断と治療戦略」(司会:氷見徹夫教授)では、本疾患の診断と治療戦略について、睡眠障害のひとつとしてとらえ、耳鼻咽喉科の役割ついて討論された。まず、滋賀医科大学睡眠学講座の宮崎総一郎教授は「睡眠障害の理解と睡眠時無呼吸への対処」について、また千葉伸太郎先生(太田総合病院)は「睡眠呼吸障害診療における医療連携と耳鼻咽喉科の役割」についてそれぞれ発表した。耳鼻咽喉科的な治療戦略のひとつとして野中聡先生(旭川医科大学)は「睡眠時無呼吸症候群と鼻呼吸障害の関係」について、新谷朋子先生(札幌医科大学)は「小児のOSASの診断と治療」、そして名倉三津佳先生(浜松医科大学)が新たな手術的治療法について発表した。



シンポジウム2は山中昇教授(和歌山県立医科大学)の司会で「扁桃病巣疾患のエビデンス−IgA腎症−」が行われた。はじめに、「IgA腎症治療における扁桃摘出術の位置づけ」について内科医、小児科医、耳鼻咽喉科医へのアンケート調査の結果を鈴本正樹先生(和歌山県立医科大学)が発表した。坂東伸幸先生(旭川医科大学)は「IgA腎症と扁桃との関連性における基礎的エビデンス」について、IgA腎症の扁桃ではケモカインレセプターの発現が高く、B細胞刺激因子(BAFF)の産生が亢進していることからこれらがIgA腎症の病態に関与している可能性を発表した。IgA腎症に対する扁桃摘出術の有効性については耳鼻咽喉科の立場から赤木博文先生(南岡山医療センター)が、腎臓内科からは堀田修先生(仙台社会保険病院腎センター)と西慎一先生(新潟大学血液浄化療法部)がそれぞれ扁摘後10年以上の観察例数十例〜数百例に上る成績を発表した。現在、IgA腎症における扁摘の効果はエビデンスが確実に蓄積され、腎臓内科においても有効な治療法と広く認識されていることが明らかにされた。



第2日目のシンポジウム3「口腔・咽頭癌診療の最前線」では司会が中島格教授(久留米大学)担当し、口腔・咽頭癌診療、特に癌治療の根治性と機能温存・再建をテーマに最近のトピックスについて討論された。まず、機能温存を目的とした放射線同時併用超選択的動注化学療法と下咽頭癌手術について荻野武先生(旭川医科大学)と中山明仁先生(北里大学)が発表した。拡大手術と機能再建手術については三谷浩樹先生(癌研有明病院)が、レーザー減量・放射線療法については坂本菊男先生が(久留米大学)発表した。そして、拡大内視鏡(narrow band imaging)による咽喉頭表在癌の診断と治療について佐藤靖夫先生(川崎市立川崎病院)が発表した。



2つの手術セミナーが若手の耳鼻咽喉科医を対象として企画された。それぞれの手術手技の適応とコツについてエキスパートが実践的なビデオを用いて発表した。ビデオ手術手技セミナーとして吉原俊雄教授(東京女子医科大学)司会のもと「副咽頭間隙へのアプローチ法」が行われた。冨田俊樹先生(慶応大学)、杉本太郎先生(東京医科歯科大学)、今田正信先生(旭川医科大学)、がそれぞれ「段階的な術式の選択法」、経耳下腺法、下顎push-up法について発表し、討論があった。もうひとつは臨床セミナーとして湯本英二教授(熊本大学)司会のもと「嚥下障害の外科的治療」が行われた。嚥下機能改善手術として輪状咽頭筋切断術と喉頭挙上術について兵頭政光先生(愛媛大学)と鮫島靖浩先生(熊本大学)がそれぞれ発表した。また、誤嚥防止手術として林達哉先生(旭川医科大学)が重度身体障害児に対する喉頭全摘術、後藤理恵子先生(香川大学)が喉頭気管分離術・気管食道吻合術について発表した。











また、2つのランチョンセミナーとして、岡本健先生(中部学院大学長)の司会で沖本二郎先生(川崎医大川崎病院呼吸器病センター長)が「肺炎の診断とQ熱感染症」についての講演がなされた。また、形浦昭克名誉教授(札幌医科大学)の司会で朝倉光司先生(市立室蘭病院)が「口腔アレルギー症候群」について講演した。






特別講演としては、今回は2つ企画した。ひとつは山下敏夫理事長(関西医科大学)が司会で、旭川医科大学第二生理学の柏柳誠教授に「味覚の生理学:世紀を跨いだ味覚研究の急展開」を講演していただいた。味覚の研究については1970年代の生理学的研究で明らかになった知見に加えて、分子生物学的手法の導入によって2000年前後から急速に理解が進んだ味の受容体機構についてわかりやすく講演された。



もうひとつは小松崎篤名誉教授(東京医科歯科大学)がに司会で、「最北の動物園の挑戦」と題し、旭川市立旭山動物園の小菅正夫園長にご講演いただいた旭山動物園は、今話題となっている動物園で、数年前は入園者数の落ち込みから廃園の危機があったが、数多くの取り組みから入園者数が日本一となった。その特徴は動物たちが本来持っている能力を遺憾なく発揮する「行動展示」であり、とても興味深く楽しいお話しを拝聴できた。この講演の後、多くの参加者が旭山動物園に出かけたと聞いている。



他に、今回は学術講演会終了後の9日午後4時から一般市民を対象とした市民公開講座「ほっておくと恐い、いびきと睡眠時無呼吸」を開催した。旭川医科大学では睡眠時無呼吸症候群を含めた睡眠障害に対して専門外来を開設するなど精力的に診療している。司会は私と精神神経科の千葉茂教授が行い、演者には旭川医科大学で実際に診療している各科の先生にお願いした。まず、睡眠時無呼吸症候群の診断と全身症状、治療ではnCPAP、歯科装具、手術治療についてそれぞれの耳鼻咽喉科、呼吸器・循環器内科、歯科の先生がそれぞれ解説した。また、不眠症などの睡眠障害とその専門外来について精神神経科の先生から解説があった。200名以上の市民が参加し、盛会に終えた。本講座によって睡眠時無呼吸に関する認識を強めることができたと思う。



一般演題の中にも興味深い演題も多数あったが、紙面の関係で述べることができない。詳細は次に発刊される日本口腔・咽頭科学会誌を参照してほしい。来年は平成18年9月7日(木)、8日(金)の両日、吉原俊雄教授(東京女子医科大学)会長のもと、東京の京王プラザホテルで開催される予定である。