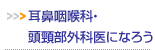耳鼻咽喉科・頭頸部外科 研究概要
当教室では耳鼻咽喉科・頭頸部外科領域を幅広く網羅する研究を行っている。また全ての教室員は1つ以上の研究テーマを持ち、研究と臨床を互いにフィードバックさせ、双方のレベルの向上を図っている。毎年、英文学術誌に多くの論文が掲載され、それらの研究成果に対し、国内はもとより国外からも高い評価を受けている。
また、海外研究留学も積極的に奨励されている。平成12年度から、アメリカ合衆国のローズウェルパーク癌研究所(バッファロー)、ヴァンダービルト大学(ナッシュビル)、アーカンソー州立大学(リトルロック)、スイスのチューリッヒ小児病院、スウェーデンのカロリンスカ研究所(ストックホルム)、南フロリダ大学モフィット癌センター(タンパ)に延べ14名の教室員を研究留学させている。
*当科における科学研究費採択の一覧を掲載しております。(クリックしてください)
I. 腫瘍・血液病態学
(高原 幹、岸部 幹、長門利純、駒林優樹、熊井琢美)
頭頸部悪性腫瘍について分子腫瘍学的、腫瘍免疫学的およびウイルス学的な多面的解析を行い、将来の分子標的治療、遺伝子診断・治療を含めたテーラーメイド診療の開発を目指している。
(1)舌癌、咽頭癌、喉頭癌、上顎癌などを含む頭頸部扁平上皮癌において発癌や進展、転移のメカニズムは十分解明されていない。当教室では免疫組織学的、分子生物学的手法を駆使してp53癌抑制遺伝子の変異、VEGFなどの血管新生因子、matrix metalloproteinase (MMP)の過剰発現、一酸化窒素合成酵素(iNOS)の発癌への関与などを解析し、研究成果を報告してきた。現在では、近年同定されたIL-21等のサイトカイン群と腫瘍との相互関係の解析や、EGFRやc-Met等に代表される癌増殖に関わる因子とその下流シグナルに関する解析を進めている。
(2)鼻性NK/T細胞リンパ腫は顔面正中部に沿って進行する破壊性壊死性肉芽腫性病変を主体とするリンパ腫であり、病態が明らかではなく、極めて予後不良な悪性腫瘍である。原渕教授が1990年にNK/T細胞リンパ腫がEBウイルス関連腫瘍であることを世界に先駆けて発見して以来、当教室では本疾患の発症や進行のメカニズムの解析を精力的に行ってきた。これまでに、本腫瘍に感染するEBウイルスの特徴として、LMP1遺伝子とLMP2A遺伝子に変異が認められ、それらが宿主の免疫系からの回避や癌原性に関与している可能性を示した。また、本腫瘍細胞の特徴として、p53、ras、β-cateninの遺伝子変異がその発症に、IL-9やIL-10などのサイトカインやCD70などの表面抗原がその増殖に、腫瘍細胞からのIP-10などのケモカインがその浸潤に関与することを示した。現在は癌関連遺伝子発現を制御するmicroRNAに関して検討を進めている。臨床と直結するデータとしては、血清EBVDNA量が特異的な腫瘍マーカーとして極めて有用であることを示し、本疾患の早期診断、治療効果判定、さらに再燃の診断に臨床応用している。これまでにスウェーデンカロリンスカ研究所Microbiology & Tumor biology center(Eva Klein教授)に2名、スイスチューリッヒ大学小児病院感染部門(David Nadal教授)に2名研究留学している(1名は現在留学中)。その他にも国内外の数多くの施設と共同研究を行っている。
(3)腫瘍免疫学の分野ではEBウイルス由来癌蛋白であるLMP-1を標的として樹立されたヘルパーT細胞が鼻性NK/T細胞リンパ腫細胞株に対し増殖抑制効果を持つことを報告した。現在では、分子治療薬の標的として有名なEpidermal Growth Factor Receptor (EGFR)由来のヘルパーT細胞を樹立し、抗腫瘍効果を検討している。さらに、分子治療と免疫療法と相乗効果に関しても検討を進めている。将来的には、臨床応用、さらに従来の治療法と組み合わせた集学的治療の確立を目指している。これまで米国バッファロー市にあるローズウェルパーク癌研究所Soldano Ferrone教授(現ピッツバーグ大学癌研究所)や米国タンパ市にあるモフィート癌研究所のEsteban Celis教授との共同研究を行っており、これまでに4名が研究留学して多数の研究成果を報告している。
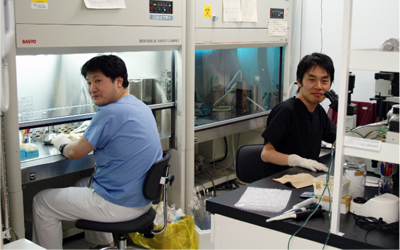
II. 免疫・感染症病態学
(林 達哉、高原 幹、岸部 幹、上田征吾、駒林優樹、熊井琢美)
扁桃病巣疾患の病態解明、急性中耳炎やアレルギー性鼻炎のワクチン療法に関して検討を進めている。
1. 扁桃の粘膜免疫機構の解析と扁桃病巣疾患の病態解明
扁桃が原病巣となり、離れた臓器に反応性の器質的または機能的傷害を引き起こす疾患を扁桃病巣疾患と呼ぶ。代表的疾患として掌蹠膿疱症、IgA腎症、胸肋鎖骨過形成症などが該当し、扁桃摘出術が著効するが、その病態は未だ不明である。我々は以前から本疾患の病態解明に力を注いできた。掌蹠膿疱症に関しては、常在菌であるα溶連菌刺激にて扁桃Tリンパ球上のCLA抗原やCCR6が過剰に発現し、選択的に病巣皮膚へのホーミングに関与すること、CTLA-4、Smad7の発現異常による扁桃T細胞活性化がα溶連菌への過剰免疫反応の根底にあることを報告してきた。近年では扁桃T細胞におけるβ-インテグリンについて検討し、皮膚へのホーミングのみならず、過剰活性化にも関与する因子であることを報告した。またIgA腎症に関しては、T細胞非依存性B細胞刺激因子(BAFF)が細菌由来DNA(CpG-ODN)刺激にて産生亢進し、IgA過剰産生の一役を担っていることを報告した。現在はBAFFよりもより選択的にIgA産生に関わっているとされるAPRIL(A ProlifeRation-Inducing Ligand)に着目して解析を進めている。
2. 小児急性中耳炎に対する細菌疫学的解析とワクチン療法の開発
小児急性中耳炎は耳鼻咽喉科領域で最も多い疾患のひとつであるが、近年の多剤耐性菌の流行で治療に抵抗する難治性中耳炎や反復性中耳炎症例が増加し、細菌疫学的見地から解析することが重要である。また、根治的治療としてはワクチン療法の開発が期待される。当教室では、1)中耳炎起炎菌の耐性化について中耳炎患児のみならず健康児を対象に疫学的調査を行い、本疾患の予防や診断基準の確立、スクリーニング法の実用化を目的として研究中である。2)中耳炎起因菌のひとつであるインフルエンザ菌に対するワクチンの開発を目的として、インフルエンザ菌P6蛋白に着目し、その抗原エピトープから構成されるワクチン療法を開発中である。本研究は原渕教授がかつて留学していた米国バッファロー市のニューヨーク州立大学小児病院Howard Faden教授やローズウェルパーク癌研究所Yasmin Thanavala教授らのグループと共同研究中であり、今まで1名が研究留学している。
3. シラカンバ花粉症の病態解明とペプチドワクチン療法の開発
シラカンバ花粉症は欧米では最も多い花粉症であり、本邦では北海道に多い。花粉症患者を含めたアレルギー患者数は増加の一途をたどっているが、いまだに根本的な治療法が見出されていないのが現状である。当教室では開設以来、本学第二病理学教室と共同でシラカンバ花粉症の新たな治療法の開発と病態の解明をテーマとして研究を行ってきた。第一にシラカンバ花粉症における抗原提示細胞についてcDNAアレイを用いて解析し、サイトカイン・ケモカイン産生ならびに共刺激分子発現を健常者と比較検討した。またシラカンバ花粉症に対するペプチドワクチン療法の開発に向けて、シラカンバの抗原エピトープの解析を行い、その一つが抑制性T細胞を誘導可能な事を見出し報告した。現在では、近年同定されたTSLP等に代表される新規アレルギーサイトカインに関しての各ヘルパーT細胞サブセットや抗原提示細胞へ及ぼす影響に関する解析も進めている。当科は平成20年より日本アレルギー学会認定施設となっており、シラカンバ花粉症患者に高率に合併する口腔アレルギー症候群(oral allergy syndrome:OAS)についての臨床的、基礎的検討も精力的に推し進めていく予定である
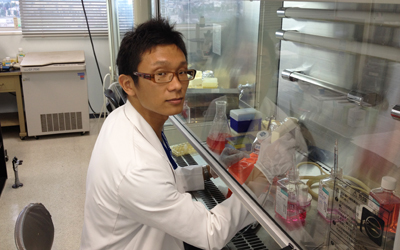
III.感覚器・運動器病態学
(片田彰博、國部 勇、野村研一郎)
喉頭機能障害に対する機能的電気刺激を用いた再運動化の研究
喉頭は口腔と肺との間に存在し、呼吸、発声、嚥下、気道防御に関与する重要な臓器である。喉頭には左右の声帯が存在し、吸気時には肺へ空気を吸い込むために声帯は開大し、発声時、嚥下時には閉鎖するという動きを行っている。これらの動きを制御している内喉頭筋は、脳神経である迷走神経から分枝する反回神経の支配を受けている。反回神経は末梢運動神経のため障害後にも再生能力を有するが、声帯の開大と閉鎖という拮抗する機能をもつ運動神経のため神経再支配後も、過誤支配のため声帯の動きが回復することはなく、麻痺した声帯は閉鎖した位置で固定する。反回神経の障害は解剖学的な位置より甲状腺、食道等の腫瘍もしくはその外科手術、または外傷等により起こることが多く、特に両側の声帯麻痺は両側の声帯が閉鎖した位置で固定するため呼吸が出来ず窒息死の危険となる。よって緊急的に気管にチューブを挿入する外科的処置を行い、その後永久的に麻痺が存在する際は、声帯の一部を切除するか、外側へ外科的に偏位させる外科的治療が取られるのが一般的である。しかしこれらの手術は、呼吸機能を優先するために行うため、発声機能が犠牲となり、また誤嚥のリスクも高くなる。我々は、麻痺した声帯の運動機能を回復させる方法として喉頭ペーシングという電気生理学的なアプローチからの研究を行っており、当教室はアメリカ合衆国テネシー州のVanderbilt大学の耳鼻咽喉科と臨床応用に向けた共同研究を2004年から行っている。喉頭ペーシングとは、喉頭の麻痺した声帯を開大させる筋肉(以下、開大筋とする)に刺激電極を埋め込み、体内埋め込み型の刺激装置から電極に電気刺激を与えることで、声帯の開大運動を行う方法である。現在までに3名が研究留学し、生体埋め込み型刺激装置の開発を進めている。