「大人が変わると子どもも変わる
-親子の関係性を育む前向き子育て-」
終了報告
2025年2月4日
二輪草セミナーは、一部を看護職キャリアセンターとの共催事業(学生と看護職のセミナー)として実施していましたが、今年度より二輪草センター独自の事業となりました。今年度は、2月4日に会場とライブ配信のハイブリット方式で行い、47名の参加(会場:17名、Zoom:30名)がありました。
WLBの視点を少し変え、忙しくても子どもと過ごす良質な時間を作るという観点から「大人が変わると子どもも変わる-親子の関係性を育む前向き子育て-」と題し、札幌医科大学保健医療学部看護学科
澤田いずみ先生にご講演いただきました。以下、エッセンスを簡単にご紹介いたします。
先生が理事をされているトリプルPとは、Positive Parenting Programの略で、オーストラリアで開発された子育て支援プログラムです。トリプルPでは5つの原則とそれに対応する17の技術があります。技術は、具体的で親がこうすれば良いというのが分かり、日常の些細なことを積み重ねることで子どもが変わることが実感できるものです。
親は子どもに対して、子どもの行動に対して、やって当たり前、できて当たり前という意識を持ちがちです。【子どもをほめる】技術では、①もっと増えてほしい行動について、②描写的に、③心から ほめるとともに、④「…しなかった」ではなく「…できた」ことを伝えることで、特定の行動を促す効果があります。
【ルールを作る】技術では、その場で子どもに注意するのではなく、事前にルールを決めることで問題が生じることを避けます。言葉で表現できるようになる3歳ぐらいのお子さんから可能で、家族会議などで子どもと話し合い、家族みんなが守ることが重要です。ポイントは、「…しない」ではなく「…する」というルールの設定で、親が肯定的な行動を発想・設定すること自体が前向き子育ての考え方です。
【はっきり穏やかな指示を与える】技術では、指示をするときに、①自分がしていることを止めて子どものそばに行き、②子どもと視線を合わせ指示し、③5~10秒待ち、④できたらほめる という対応をします。
最後に、【自分の子どもへの期待を省みる】では、子どもに対して無理な期待や高いものを求めることで挫折の機会につながり得ることから、子どもがうまくいかない時、ルールがうまく守られない時は、親が期待するものが子どもに合っているのか点検することが必要になります。
チャットを含めた質疑では、子どもが他人の気持ちを理解するためには、まず子どもの気持ちを親が言語化し、自分の気持ちを理解してもらったり大事にしてもらう体験をすることが大事であること、ルールを決めるときにも自分だけではなく周りがどう感じるかを考えられるようにすることなど助言いただきました。大人と同じ完成度にできないとやらないお子さんへの対応については、親の期待を省みるという視点で振り返るなど参加者ご自身が考える力を身に着けられていました。明日の朝は、子どもを優しく起こして10秒待ってみようと思ったなどの感想もありました。
ご講演の中では、先生ご自身がご家庭の中で、10秒待ったら笑顔で朝を迎えられた体験、スマートフォン使用のルールの話し合い、お子さんが学童保育でけんかのしないためのルールを作成したことなど多くの体験談をお話しいただきました。
自分たちのお子さんへの関わりを振り返り、すぐに実行できる多くのヒントをいただきました。子育てのみならず、職場のなかでも応用できる内容が盛りだくさんでした。札幌から来校いただきましたこと、多くの父母にエールを送ってくださいましたことにお礼申し上げます。
看護職キャリア支援職場適応担当 平塚 志保
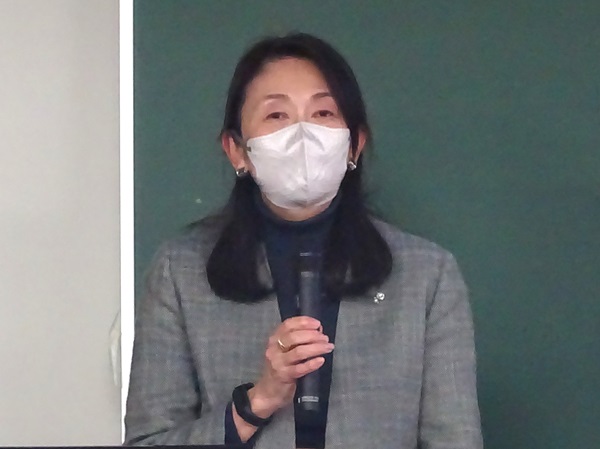 |
 |